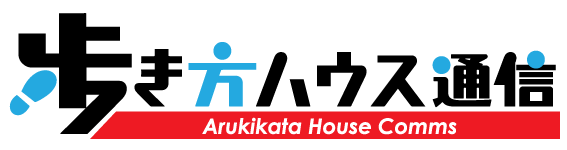3年前、まだ高校2年生だった私が訪れた西アフリカに位置するセネガル共和国。若いうちに“現地で見る”ことの意義とは何か。移動が難しくなった今こそ、体験を振り返り、これからの旅の在り方について考えた。
「アフリカ大陸」に対する漠然とした憧れ
なぜセネガルだったのか。それは偶然の縁である。
はじめに興味を抱いたのは、「アフリカ大陸」という漠然としたものだった。
出会いをくれたのは、地元横浜で毎年開催されている「よこはま国際フェスタ」というイベントで、世界をフィールドに活躍されている方々のブース、世界各国の文化を楽しめるパフォーマンスやワークショップ、料理、物販が集まるもの。その中でも特に気になったのがアフリカだったのだ。

これまで味わったことのない、陽気でかっこいいライブ演奏に老若男女が自然と集まり表現を楽しむ空間。初めて会ったとは思えないあのフレンドリーな人たち。布の柄ひとつとってもなぜこんなにも惹かれてしまうのだろう。
素直な土地への興味と、アフリカと日本をまたいで生きている方々との縁が重なり、いつの間にか「実際にこの足で訪れたら、自分は何を思うのだろう」という気持ちが湧き上がってきた。そんな頃、セネガルと出会ったのだ。
第一歩目
繋げてくださったのは、AFRICULTUREという団体で、伝統音楽を通じた活動や現地でのコーディネートをされている方だった。もともと知り合いだったということもあり、自分で旅費は出すという条件のもと、親の了承を受けた私は、高校2年生の夏休みにセネガル行きを決意した。現地で主に使われている日常言語であるウォロフ語を知り合いの方々に教えてもらったが、どれも幸せな例文ばかりでどんどん胸が高鳴ったのを覚えている。
大きなバックパックを背負い、パリを経由したのちたどり着いたレオポール・セダール・サンゴール国際空港。セネガルの首都、ダカールだ。飛行機の遅れと、見知らぬ人々、そしてなかなか繋がらないWi-fi 。本当にその知人に会えるのかという戸惑いと、いよいよたどり着いたのだという実感に嬉しさと少しばかりの不安が伴った。
もう夜だったが、ターミナルの外は思ったよりにぎやかで、様々な音と人が行き交い、オレンジ色の明かりは強く反射しあっていた。空港を出てまっすぐ歩いていくと知っている声。知人に会える喜びはこんなにも大きかっただろうか。便利で不自由ない日本での生活を抜け出した高校生の私が、アフリカの魅力にすっと触れたような、一歩目を踏み込んだ瞬間だったように思う。
セネガルでの日常体験
目を覚まし、ブティック(キヨスクのようなもの)でフランスパンを買う。お世話になるコーディネーターの親戚の家に遊びに行き、道中で露天商から買ったコーヒーや水を飲む。たまに市場へ出かけ、買い物ついでに立ち話をし、夕暮れの海でまったりしていたらまた誰かに話しかけられる。
夜にはどこからか音楽が聞こえてきて、外を見ると人々が音のなる方へ歩いて行くので、私たちも歩いて行く。伝統衣装を身にまとった人々が、口を大きく開けて楽しそうに踊っている。私も楽しくなってくる。星が綺麗で、眺めていたらあれは「ビデウ」だと地元の子が教えてくれた。
歌を歌うとき、絵を描くときは言語の壁はすんなりとなくなっていたけれど、私もそうして少しずつ、セネガルでのコミュニケーションを学び、暮らし方を覚えていった。
居ていい空間
外に座っているだけで、誰かが声をかけてくれる。新しく訪れた家でも座って座って、これ飲んで、ともてなしてくれた。セネガルにも日本のおもてなしのような感覚があるらしく、現地では「テランガ」と呼ばれている。遠い国からきた私に居場所をつくってくれる彼らへの感謝と、真のおもてなしとは何なのだろうかというモヤモヤが湧き上がっていた。私の記憶の中のセネガルは優しい空間だった。

直接会うということ
ケベメールという郊外のまちへ訪れた。私が所属しているバオバブの会(セネガルで教育支援を行う市民団体)が関わっている地域だ。事業のひとつに、セネガルの女性がつくった小物を日本で売り、その売上金を還元することで、女性の自立支援や子どもの教育支援につなげるものがある。その工房へ行きたかったのだ。今までも写真などで見たことはあったが、実際に訪れると親近感が高まった。ちなみに、セネガル料理のチェブジェンをみなで囲って食べる時間が私は大好きだった。
ケベメールまで行くと、まちなかをロバが歩いている。内陸特有の暑さが押し寄せ、人々は、木陰に集まり、商売や団らんをしている。植物や乗り物、壁にあるペイントもかっこいい。帰国後、例えばイベントで販売をするときなどにもこの景色が浮かぶ。物事の背景にある街や人を知っていることが、今でも私の日常を刺激するのだ。
まちの発展
都心部はみるみる変化していた。私が滞在していた2週間半の間にも、スタジアム建設は背を伸ばし、道路は道筋を変えた。空港もどんどん整っているところなのだという。海辺はトレーニングスペースが充実していたし、街中には高いビルも高級そうな家もあった。教育を受ける子ども達も増えているらしい。きっと3年たった現在はさらに発展しているだろう。どんどん発展していくセネガルで彼らは何を思うのだろうか。発展の先にどのようなセネガルがあるのだろう。何度でも行きたくなってしまうのだ。
よそ者と文化伝承
発展していく中で何が残るのか、何が失われるのか。たった数日しか滞在していなかった私には想像の限界があるが、それでも、魅力を書き記すことならできるのではないかなどと考えるのだ。また滞在中に、さまざまな文化に触れることができたが、よそ者の私がその中に居させてもらうとき、きっと彼らは自分の文化を自覚したのではないかなどと今は思うのだ。継承がいかに可能かは分からないけれども、外にも中にも居られる私たちの役割が何やらあるような気がしている。
これからの旅
2020年のパンデミックはもちろんアフリカでも起こっている。時間と資金があれば、自分の見たい景色、会いたい人がいる場所へいつでもアクセスできていた日常が失われ、移動に対するハードルが急に上がった。実際オンラインで遠くの人と会話することは容易であり、またストリートビューやVRなどの技術を使えば疑似的に街を歩くことも可能であることに気づかされた。
しかしそれでもなお、私たちが感じる ”実際に見たい” という気持ちはどうしようもなく生まれるものなのではないか。偶然から生まれる、あの光景や交流が、その後の人生にもずっと影響するこの感覚はやはり実際に足を踏み入れてなお湧き上がるものだと思う。
現在私は日本の大学で、社会学や「まちづくり」を学んでいる。時代や社会の変化によって、変わるもの、変わらないものとは何か。誰もが無理をしないでも社会に受け入れられながら生きていける社会とは何か。まちをどう活かして行けば出会いが生まれるのだろうか。そのような思考の根っこのどこかに、セネガルでの体験がいつもある気がするのだ。